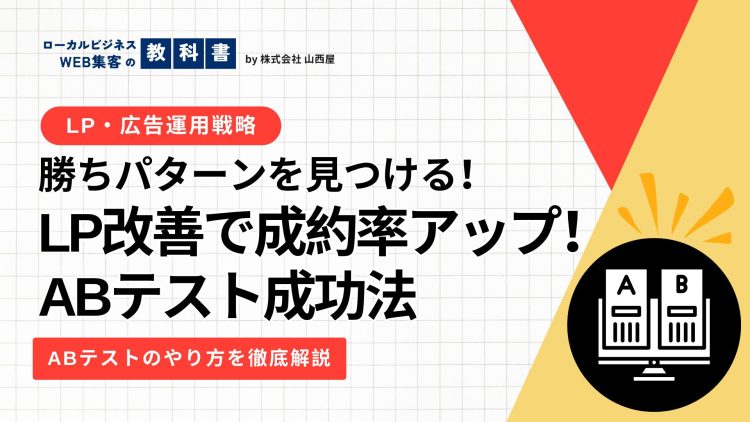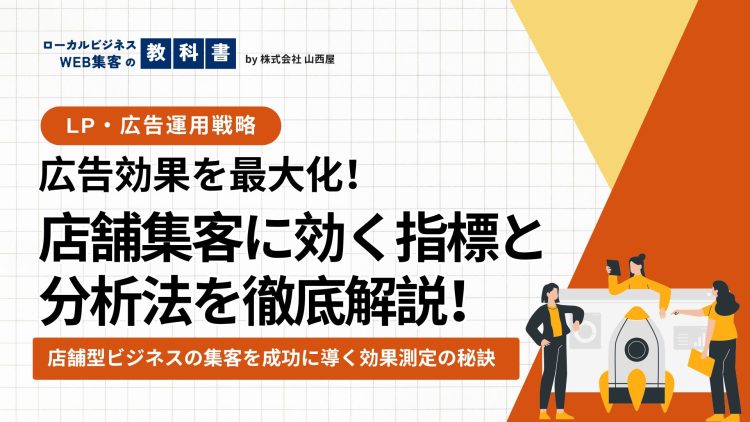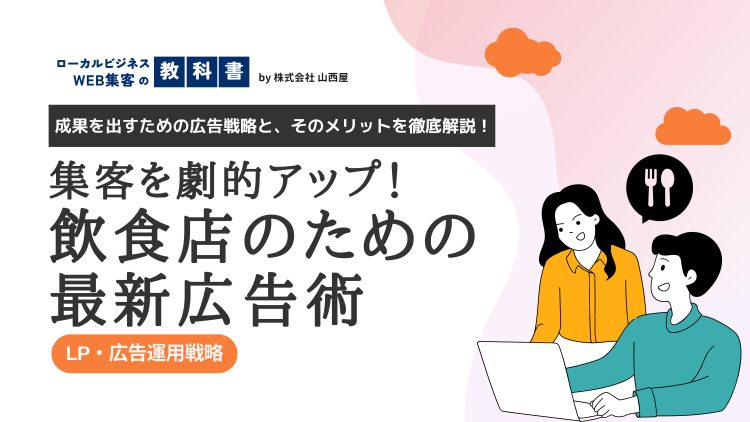Webビジネスを行う際によく聞くランディングページ。
しかし名前は聞いたことがあるけれど、具体的には何か分からない…という方も多いのではないでしょうか。
今回は初心者向けにランディングページの基礎知識を説明していきます。
広義のランディングページとは
広義のランディングページとは、ユーザーがウェブサイトで最初にアクセスする(=「着地(landing)」する)webページのことを指します。
訪問者が最初にアクセスするページであれば、それがトップページであるか下層ページであるかを問わず、すべて広義のランディングページに該当します。
例えば、検索エンジンの検索結果からサイトの「会社案内」ページに直接アクセスした場合、その「会社案内」ページがランディングページとなります。
広義のランディングページへの主な流入経路には
- GoogleやYahoo!などの検索エンジンからの自然検索(オーガニック検索)
- 検索エンジン上部に表示されるリスティング広告
- FacebookやTwitterなどのSNSからのアクセス
- メールマガジンのURLリンク
- 他サイトからの被リンク
- 紙媒体の二次元バーコードからのアクセス
などが存在します。
Googleアナリティクスなどのアクセス解析ツールで扱われるランディングページとは、この広義の意味を指します。
狭義のランディングページ(LP)とは
狭義のランディングページ(LP)とは、ユーザーの具体的なアクション獲得を目的として特化した縦長1ページ構成のウェブページを指します。
一般的にwebマーケティング業界では、「ランディングページ」と言えばこの狭義の意味を指します。
具体的には
- 商品購入
- 資料請求
- 問い合わせ
- セミナー・無料登録・試供品申込み
などの成果(コンバージョン)獲得に焦点を絞ったページが該当します。
以下で解説するランディングページ(LP)は狭義の意味を指しています。
ランディングページ(LP)の特徴とHPとの違い

それでは、ランディングページにはどのような特徴があるのでしょうか。
また、集客対策の一つであるホームページとどのような違いがあるのでしょうか。
ランディングページ(LP)の特徴
ランディングページは縦長1ページ構成のウェブページを指します。
これは営業トークやセールスレターを縦長1枚のページにまとめたような形式で、ユーザーは下にスクロールしながら情報を得ていきます。
ランディングページはお問い合わせや申し込みフォームなどのコンバージョンに直接つながるリンクのみで、それ以外のリンクが極めて少ないことも特徴です。
これは、ユーザーの注意を分散させないようにするという理由で、他ページへの導線はあえて制限されています。
また、通常のウェブサイトと比べてデザインの自由度が高く、画面全体を使ったインパクトのある表現が可能です。
キャッチコピーや見出しには大きなフォントやデザイン性の高い画像が使われ、ユーザーの興味を引きつけるよう工夫されています。
さらに、スクロールに合わせた動きのあるデザインや、目立つコンバージョンボタンの配置など、視覚的な効果が重視されています。
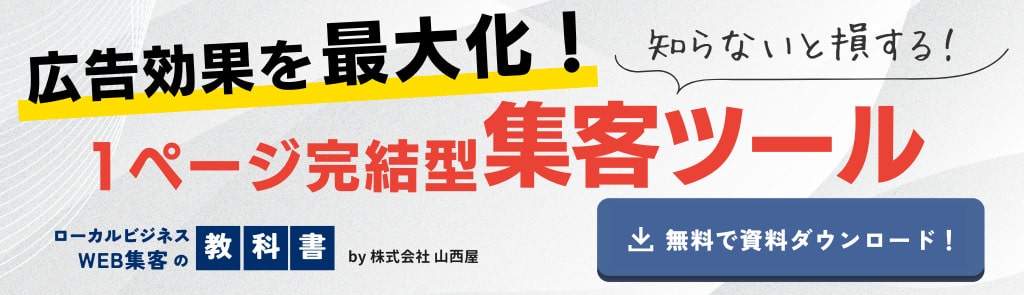
ランディングページ(LP)の特徴とHPとの違い
ランディングページとホームページ(HP)は、構造と目的において明確な違いがあります。
ランディングページは基本的に1ページ完結の縦長フォーマットで、商品購入や資料請求など特定のアクションを促すことを目的としています。
対してHPは商品購入や資料請求以外にも、会社概要、製品紹介、採用情報など、複数ページや多くのコンテンツから成っています。
HPは利用する顧客によって複数の目的があり、その複数の情報を整理して掲載するという役割を担っているからです。
さらに、集客方法も異なります。
ランディングページはSEO対策での集客が期待できずリスティング広告などの有料広告と組み合わせることが一般的で、コストがかかりがちです。
対してHPはSEO対策を行うことで自然検索からの流入が期待できるため、比較的低コストで運用可能です。
これらの違いを理解し、目的に応じた適切な使い分けが成功のカギとなります。
ランディングページ(LP)の メリットとデメリット
ランディングページはwebビジネスにおいて重要ですが、闇雲に作ればいいという訳ではありません。
ランディングページには、明確なメリットとデメリットが存在します。
ランディングページのメリット
メリットとしては、まず購入や申込みなどの具体的な成果を狙いやすい点が挙げられます。
ユーザーが求める情報を1ページに集約でき、ナビゲーションリンクも少なく、伝えたい順番で商品やサービスを訴求できるため、ユーザーの離脱率が下がりコンバージョン率を高める効果があります。
また、単一ページで構成されているため、分析・改善がしやすくPDCAサイクルを回しやすいのも強みです。
さらに、イメージダウンを避けながら強いセールスができる点や、流入元によって複数のLPパターンを用意できる柔軟性も魅力です。
ランディングページのデメリット
一方でデメリットとしては、通常のホームページよりWEBデザインの専門知識が必要になり、ユーザーに訴求できるようにテキストも練り込んでつくらなければならないため、労力・経済的に制作コストが高くなりがちな点が挙げられます。
また、訴求力を高めるため文字を画像にすることも多いため、自然検索からの流入を期待しにくくSEO対策には弱い傾向にあります。
そのため通常はリスティング広告などの広告運用と組み合わせる必要があります。
リスティング広告はクリックするごとに費用が発生し、キーワードによっては1クリックあたりの費用が数千円かかることも。
これは継続的なランニングコストにつながります。
さらに、特定の商品・サービスに特化している性質上、複数の商品を紹介したい場合は別のLPを作成する必要があり、コスト負担が増加します。
直帰率(ユーザーが最初にアクセスしたページだけを見てウェブサイトを離れる率)が高くなりやすい点も課題の一つです。
ランディングページは、ユーザーにとって「購入するか離脱するか」の二択となりやすく、サイト内の回遊性が低くなるためです。
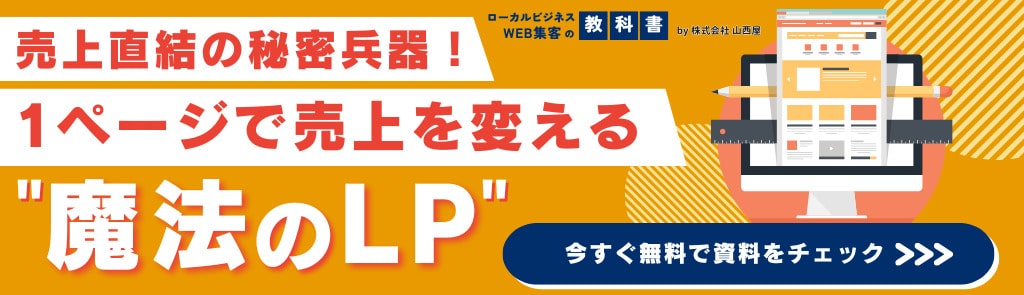
ランディングページ(LP)を効果的に活用する方法
ランディングページを効果的に活用するには、いくつかの重要なポイントがあります。
広告を多用してアクセス数を上げる
まず、ランディングページはそれ自体でSEO集客を期待することが難しいため、リスティング広告やSNS広告などを活用してアクセス数を増やすことが必須です。
特にリスティング広告は即効性が高く、ターゲットユーザーにリーチしやすい特徴があります。
また、既存のホームページやオウンドメディアとランディングページを連携させる方法も効果的です。
SEOに強い企業サイトやブログからランディングページへ誘導することで、コストを抑えながらコンバージョン率を向上させることができます。
スマートフォンに対応する
現代ではスマートフォン対応も不可欠です。
アクセスの多くがスマホからのため、スマホ最適化されていないランディングページは離脱率が高くなり、せっかくの機会を逃してしまいます。
必ずスマートフォン対応のページを設定しましょう。
ユーザーの動きを分析し改善を行う
さらに、分析ツールを活用してユーザーの行動を分析し、継続的に改善(LPO:ランディングページ最適化)を行うことも重要です。
完璧なランディングページを最初から作ることは難しいため、データに基づいて少しずつ改善していくプロセスが成功への鍵となります。
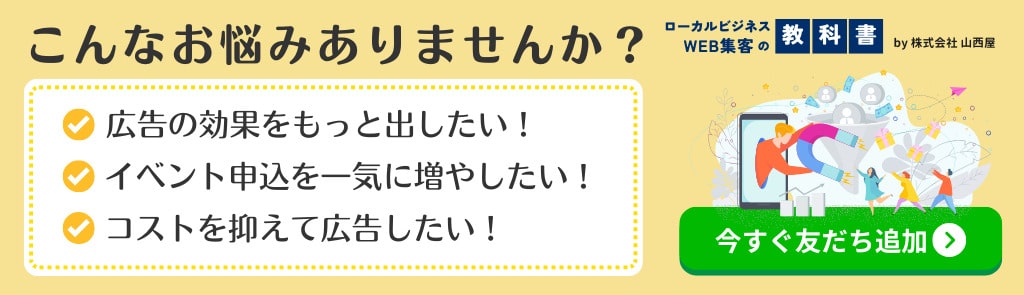
【まとめ】LP(ランディングページ)とは何か?
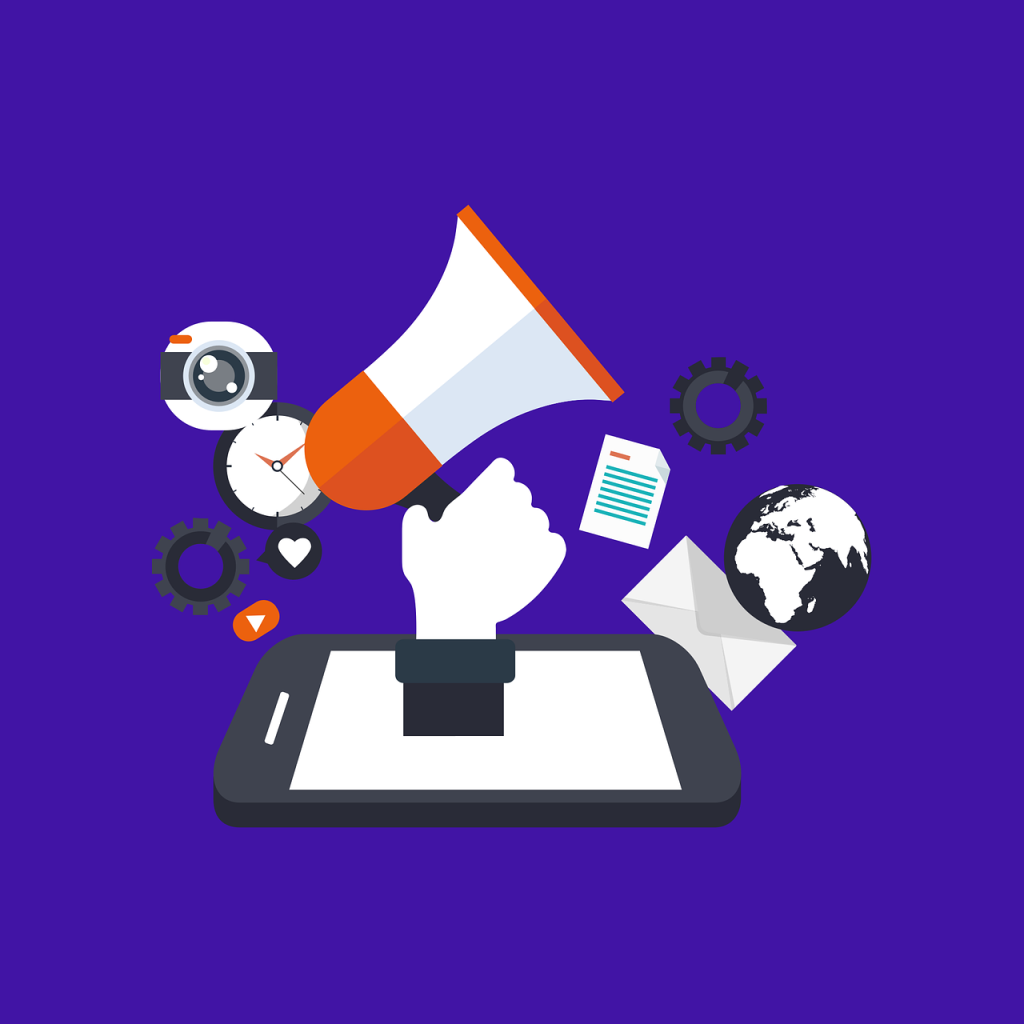
ランディングページ(LP)は、特定の目的に特化した単一ページの設計で、高いコンバージョン率を実現できるWeb施策です。
リスティング広告との連携やスマホ対応、継続的な改善を行うことで、効果的なマーケティングツールとして活用できます。
まずは、HPとの違いやメリット・デメリットを把握し、目的に合わせた適切な運用戦略を練りましょう。
ただし、ランディングページは簡単には作れません。
HPとは別に専門的な知識が必要になるため、自社で作り方が分からず難しい場合は業者に依頼しサポートしてもらうのがおすすめです。
▼LP制作のご相談も受付中です!
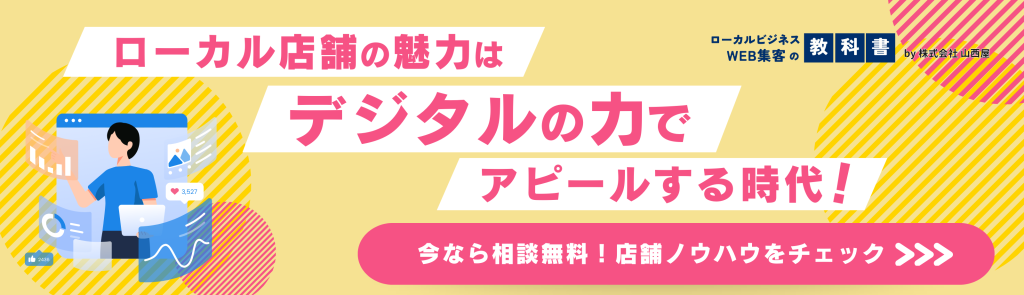

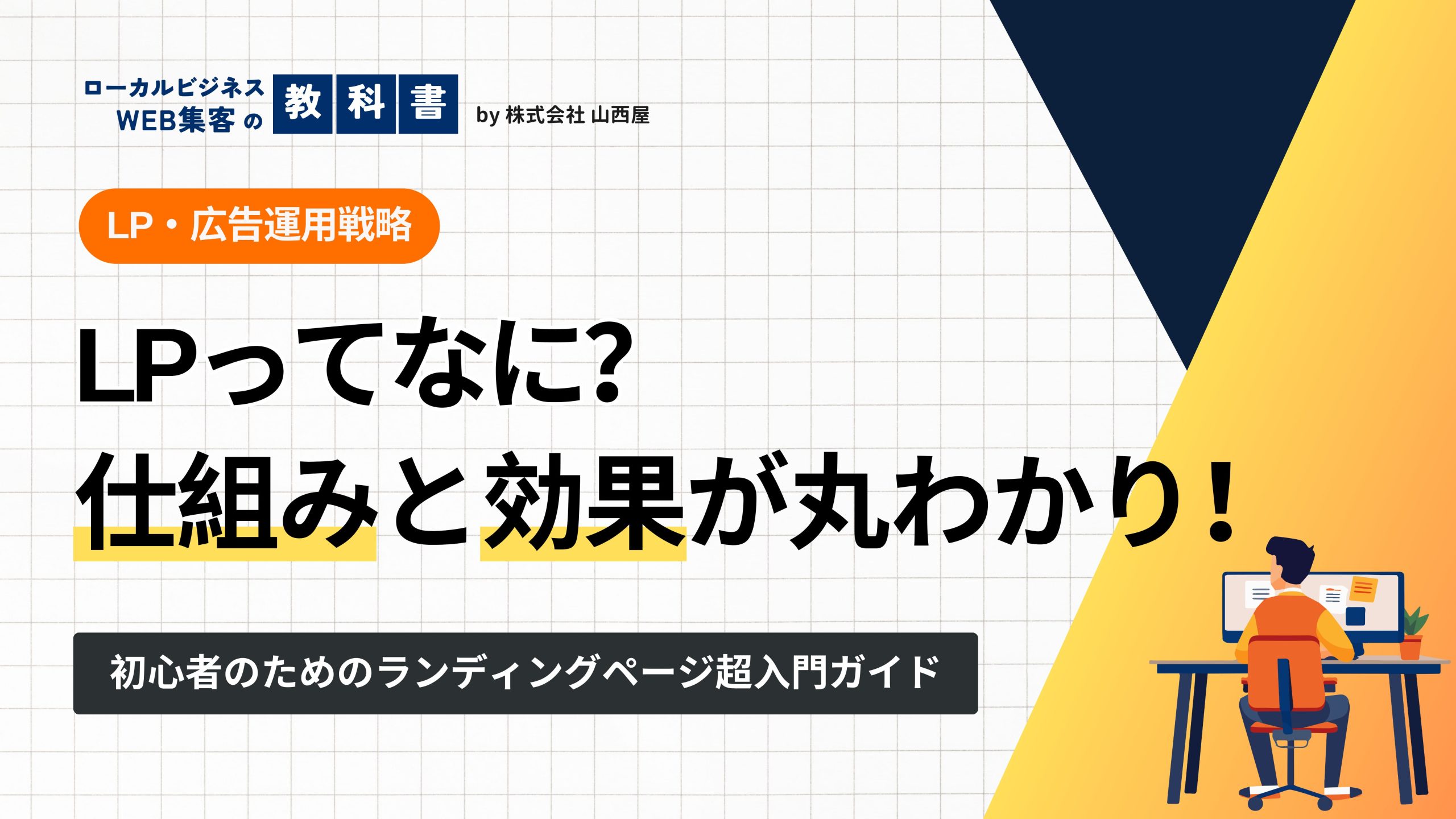



を活用しよう-750x422.jpg)